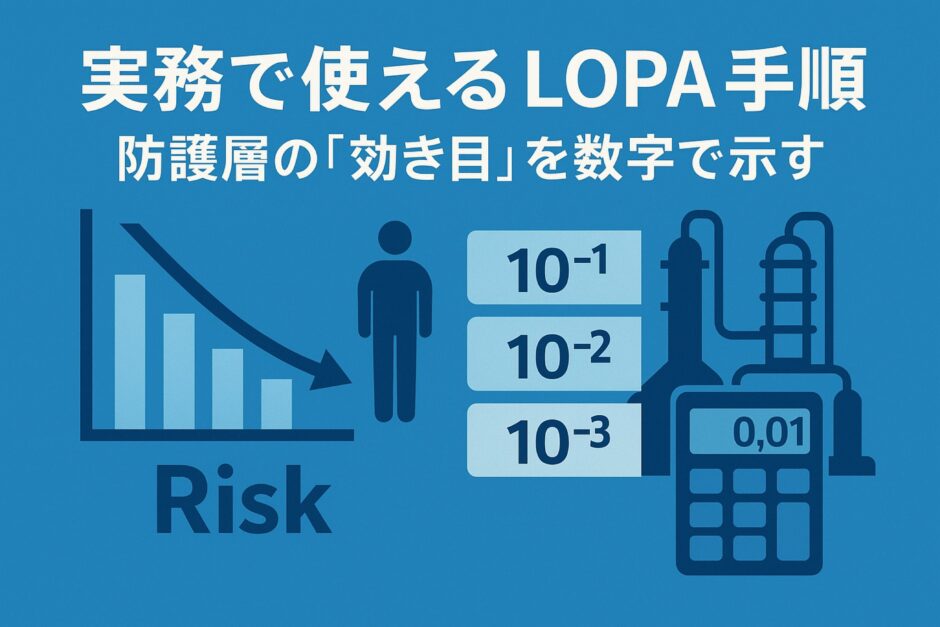HAZOPでリスクシナリオを洗い出したあと、
- 「今の安全対策で本当に足りているのか」
- 「どこまで対策すれば“やり過ぎでも不足でもない”と言えるのか」
を判断する場面が出てきます。
LOPA(Layer of Protection Analysis)は、重要なシナリオについて 防護層(IPL)の“効き目”を数値で評価し、現状のリスクが許容範囲かどうかを論理的に説明するための手法 です。
本記事では、化学プラントを想定して、LOPAを実務でどう進めるかを、手順書レベルの粒度で整理します。
1. LOPAで目指すゴール
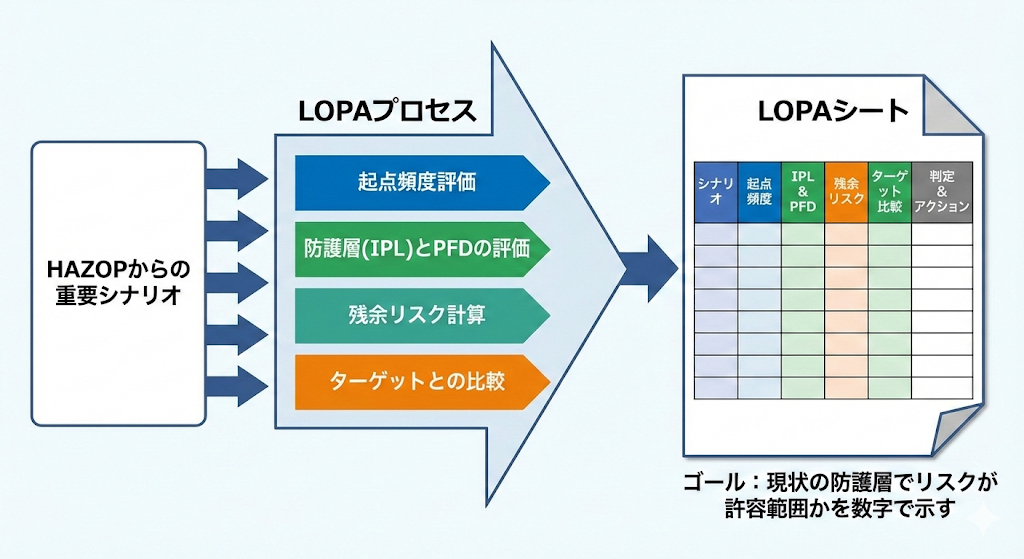
LOPAのゴールはシンプルです。
重要なリスクシナリオごとに「現状の防護層で残余リスクが許容範囲かどうか」 を数字で示すこと
そのために、シナリオごとに次を整理した LOPAシート を作ります。
- 起点事象の頻度(どのくらい起こりそうか)
- 有効な防護層(IPL)と、そのリスク低減効果(PFD)
- 結果としての残余リスク頻度
- 会社が定めた許容リスク基準(ターゲット頻度)との比較
- 追加対策の要否と方向性
2. LOPAの前に決めておくべき3つのルール
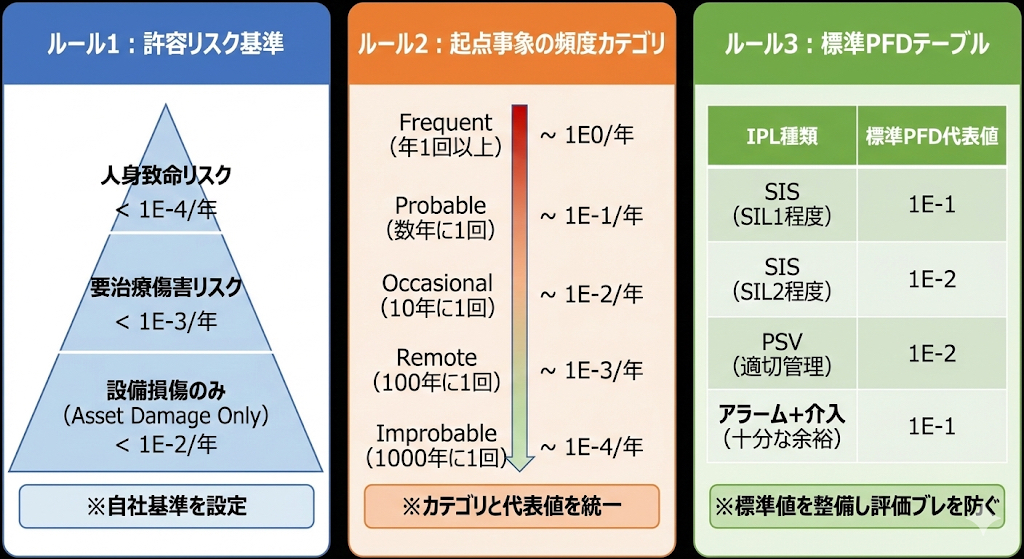
いきなり計算に入る前に、会社として 共通ルール を決めておくと、LOPA結果の一貫性が保てます。
2-1. 許容リスク基準(ターゲット頻度)
まず、「どのレベルまでリスクを下げれば“許容”とするか」を決めます。
例(※あくまで一例):
- 人身致命リスク:シナリオごとの許容頻度 1×10⁻⁴ /年 以下
- 要治療の傷害リスク:1×10⁻³ /年 以下
- 大きな設備損傷のみ:1×10⁻² /年 以下
自社の安全方針、法令要求(高圧ガス・危険物など)、業界ガイドラインとの整合を取りながら決めておきます。
2-2. 起点事象の頻度カテゴリ
起点頻度は、実績や信頼性データから 厳密な数値 を出せるケースもありますが、実務では次のような カテゴリ+代表値 で扱うことが多いです。
| カテゴリ | イメージ | 代表値の例 |
| Frequent | 年1回以上起こり得る | 1×10⁰ /年 |
| Probable | 数年に1回程度 | 1×10⁻¹ /年 |
| Occasional | 10年に1回程度 | 1×10⁻² /年 |
| Remote | 100年に1回程度 | 1×10⁻³ /年 |
| Improbable | 1000年に1回程度 | 1×10⁻⁴ /年 |
※上記の頻度カテゴリと代表値は、本記事で示した一例です。
実務では、自社の設備特性・トラブル実績・業界ガイドライン等を踏まえ、会社として統一したカテゴリと代表値 を定めておくことが重要です。
HAZOPで「しばしば起こりそう」「滅多にない」などと議論された内容も参考にしつつ、類似事例・設備のトラブル実績・データベースを総合してカテゴリを決めます。
2-3. IPLごとの標準PFDテーブル
防護層(IPL:Independent Protection Layer)の種類ごとに、標準的なリスク低減効果 PFD(Probability of Failure on Demand) を決めておきます。
例(※実務では自社基準を策定してください):
- 高高液位インターロック(SIS SIL1程度):PFD = 1×10⁻¹
- 高高液位インターロック(SIS SIL2程度):PFD = 1×10⁻²
- 適切に設計・整備されたPSV:PFD = 1×10⁻²
- アラーム+オペレーター介入(余裕時間と教育が十分):PFD = 1×10⁻¹
- 手順・注意喚起だけ:原則 IPL としてはカウントしない(PFD≒1)
本記事のPFD値は、LOPAのイメージをつかむための代表値です。
実務では、IEC 61511 等の規格や社内標準、実際のSIS設計・試験周期・PSV管理水準に基づき、自社として妥当なPFD を定めて運用する必要があります。
この「標準PFD表」を用意しておくことで、設備ごとに評価がブレるのを防げます。
3. Step1:HAZOPからLOPA対象シナリオを選ぶ
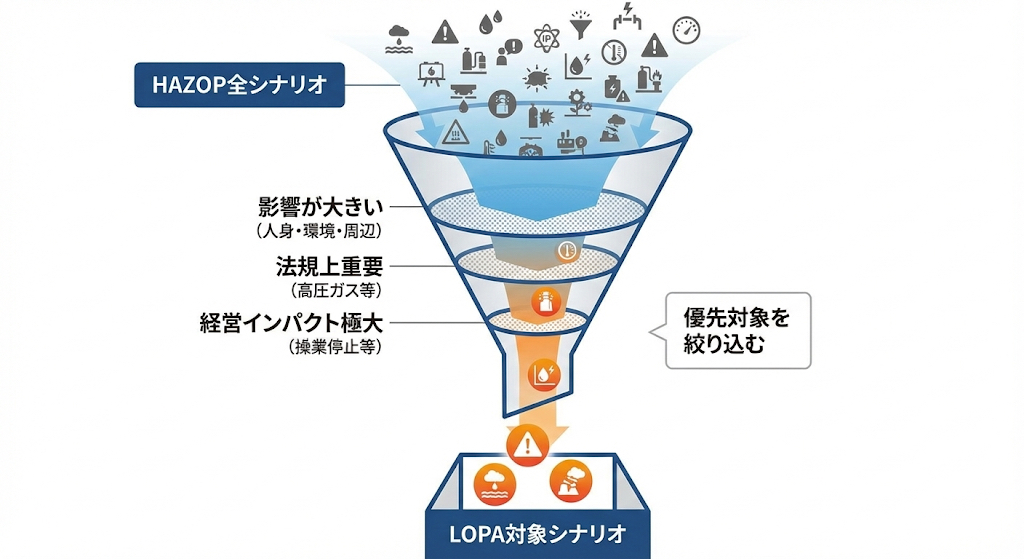
LOPAは、すべてのHAZOPシナリオに適用する必要はありません。
次のような条件のシナリオを 優先対象 とします。
- 人身・周辺・環境への影響が大きい
- 法規上も重要(高圧ガスの重大事故想定など)
- 一度起きると操業・経営インパクトが極めて大きい
例:
溶剤供給ラインでの 過大流量 → 反応器オーバーフロー → 可燃性溶剤漏洩 → 引火
といったシナリオが典型です。
4. Step2:シナリオを「起点事象」と「結果事象」に整理する
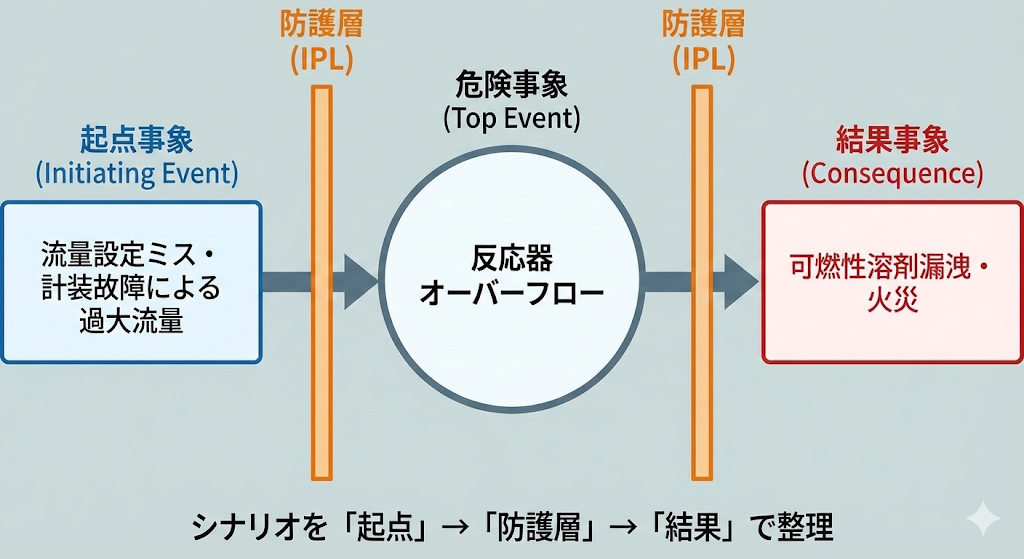
次に、対象シナリオを ボウタイ図のイメージ で整理します。
例)
- 起点事象:
「流量設定ミスや計装故障により、給液流量が上限を超える」 - 結果事象:
「反応器がオーバーフローし、可燃性溶剤が設備外に漏洩、火災に至る」
LOPAでは、「どの起点が、どの防護層を経て、どの結果に至るか」 を明確にします。
5. Step3:起点事象の頻度を決める
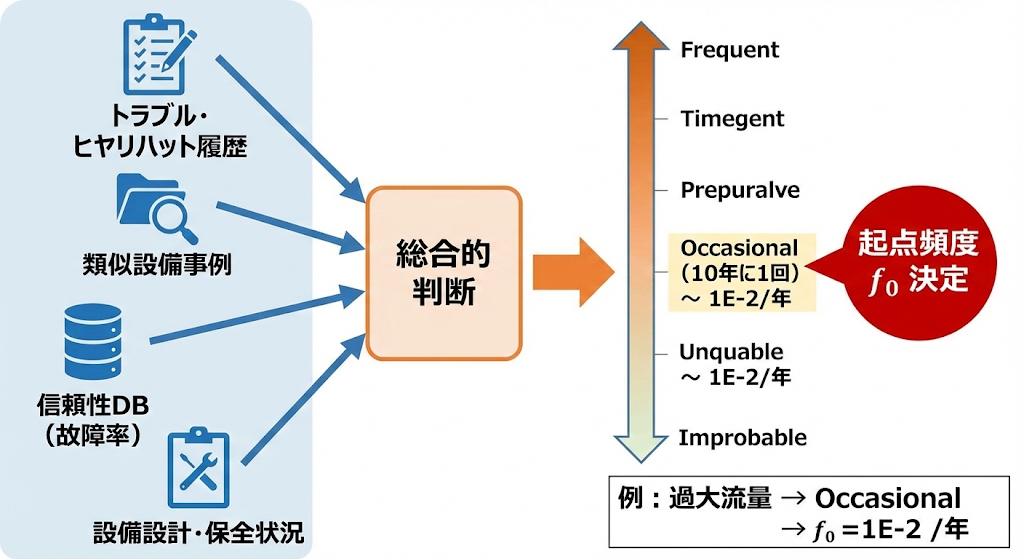
2章で決めた頻度カテゴリを使って、
シナリオごとの 起点頻度 f₀ [1/年] を決めます。
例(数字はイメージ):
- 「流量設定ミス・計装トラブルにより過大流量になる」
→ 「10年に1回程度あり得る」
→ カテゴリ:Occasional → f₀ = 1×10⁻² /年
判断には次の情報を総合的に用います。
- 自工場およびグループ工場のトラブル・ヒヤリハット履歴
- 類似設備での事例
- 信頼性データベース(故障率)
- 設備の設計・保全状況、運転モードの複雑さ など
6. Step4:有効な防護層(IPL)を洗い出す

続いて、そのシナリオに対して 実際に効いている防護層 を列挙します。
例)
- 高流量アラーム(FAH-101)+オペレーター介入
- 反応器液位高アラーム(LAH-101)+オペレーター介入
- 高高液位インターロック(LAHH-101 による自動給液遮断)
- PSVによる圧力保護 など
6-1. IPLとしてカウントするための4条件
一般に、IPLとして認めるには、次の条件を満たす必要があります。
- 独立性(Independent)
起点事象と同じ故障モードで潰れないこと。 - 特異性(Specific)
対象シナリオに対して確実に動作すること。 - 信頼性(Dependable)
所定のPFDを満たす設計・保全・試験が行われていること。 - 検証可能性(Auditable)
点検・試験記録などにより、機能を確認できること。
単に「画面を見ていれば気づくはず」「ベテランが多い」といった要素は、通常 IPL にはカウントしません。
7. Step5:各IPLにPFDを割り当てる
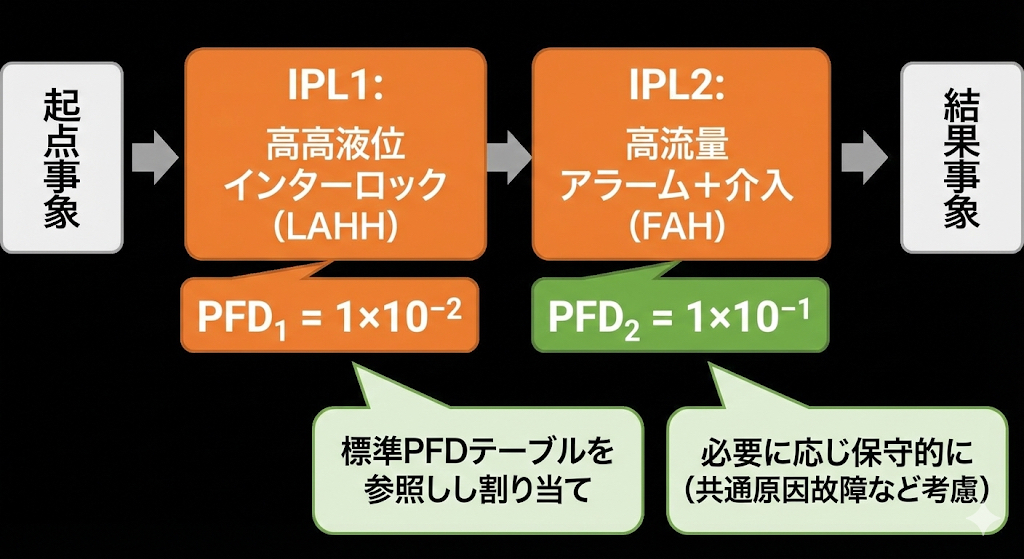
2章で整備した標準PFDテーブルに従い、挙げたIPLごとにPFDを割り当てます。
例)
- IPL1:高高液位インターロック(LAHH-101 → 自動遮断)
→ PFD₁ = 1×10⁻² - IPL2:高流量アラーム(FAH-101)+オペレーター介入
→ PFD₂ = 1×10⁻¹
この際、
- 試験周期
- 共通原因故障(電源喪失・計装系統の共通性)
- 人的要因(夜勤・負荷の高い監視など)
も考慮し、必要に応じて PFDを保守的に 取ります。
8. Step6:残余リスク頻度を計算し、ターゲットと比較する
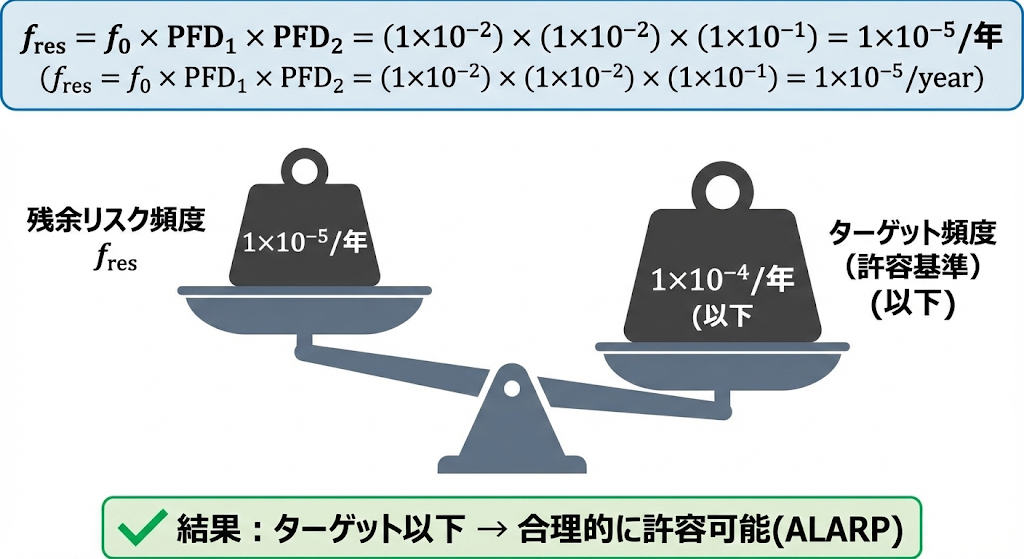
残余リスク頻度 f_res は、次式で求めます。
f_res = f₀ × PFD₁ × PFD₂ × …
ここでの掛け算は、採用しているIPL同士が 「独立している」 ことを前提としています。
共通原因故障(同一電源・同一計装系統・同一メンテナンス手順など)の影響が大きい場合は、PFDの見積りをより保守的にする、あるいは別途補正を行う必要があります。
先ほどの例を用いると、
- f₀ = 1×10⁻² /年
- PFD₁ = 1×10⁻²
- PFD₂ = 1×10⁻¹
よって、
f_res = 10⁻² × 10⁻² × 10⁻¹ = 1×10⁻⁵ /年
となります。
これを、あらかじめ決めたターゲット頻度と比較します。
- ターゲット(致命リスク):1×10⁻⁴ /年 以下
- 結果:1×10⁻⁵ /年
→ 1桁以上余裕があるため、「現状の防護層で合理的に許容可能(ALARP)」 と判断できます。
もし、
- f_res = 3×10⁻⁴ /年
- ターゲット:1×10⁻⁴ /年
のようにターゲットを上回る場合は、次のような方針を検討します。
- 追加IPL(SIS増設、二重遮断など)の導入
- 既存IPLの信頼性強化(試験周期短縮、設計見直し)
- プロセス条件の見直し(運転範囲制限、在庫量削減)
- 起点頻度を下げる運転方法・設備構成への変更 など
9. Step7:対策方針を決め、アクション管理へ渡す
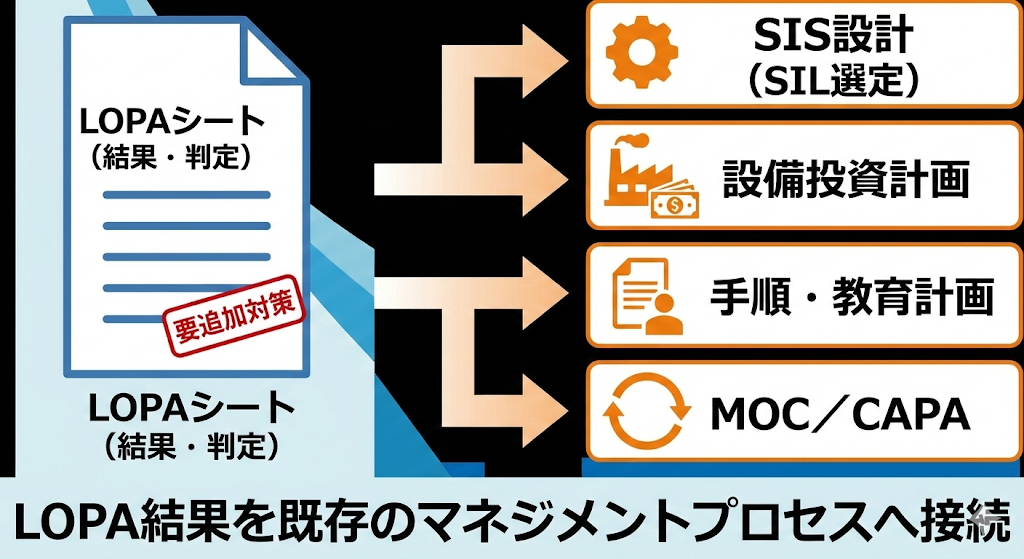
LOPAの最終アウトプットは、単なる計算結果ではなく、次をまとめた LOPAシート です。
- シナリオ名・起点事象・結果事象
- 起点頻度 f₀
- 採用するIPLの一覧と PFD
- 残余リスク頻度 f_res
- ターゲット頻度との比較結果
- 判断(Accept/要追加対策)
- 追加対策案・担当部署・完了期限
ここから、
- SIS設計(SIL選定)
- 設備投資計画
- 手順・教育計画
- MOC/CAPA
といった既存のマネジメントプロセスに接続していきます。
10. HAZOP・QRAとの関係
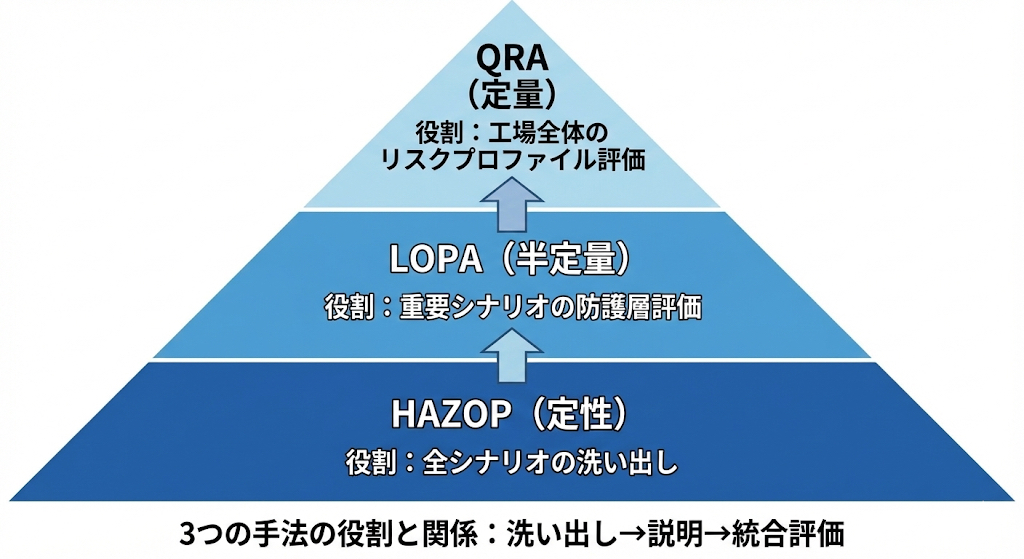
整理すると、3つの役割は次のようになります。
- HAZOP:
プロセスのハザードとリスクシナリオを漏れなく洗い出す。 - LOPA:
重要シナリオに絞り、
防護層の組み合わせで どこまでリスクが下がるかを定量評価 する。 - QRA:
複数シナリオを統合し、工場・地域全体としての
リスクプロファイル(個別リスク・社会的リスク) を評価する。
HAZOPで作った「リスクシナリオのカタログ」を、
LOPAで「どこまで対策すべきか」の議論につなげ、
QRAで「工場全体として社会にどう説明するか」に展開していくイメージです。
まとめ:LOPAは「防護層の妥当性を説明するための道具」
本記事では、LOPAの実務手順を
- 許容リスク・頻度カテゴリ・標準PFDのルール作り
- HAZOPからのシナリオ選定
- 起点事象の頻度設定
- 有効なIPLの抽出
- IPLへのPFD割り当て
- 残余リスク頻度とターゲット頻度の比較
- 対策方針とアクション管理
という流れで整理しました。LOPAは、難しい数式を振り回すためのものではなく、「このレベルの防護層を入れているから、この頻度まではリスクを下げられている」と、経営層・現場・社会に対して 合理的に説明するための道具 です。
HAZOPと組み合わせて活用することで、化学プラントのリスクマネジメントを「感覚」から「説明できるレベル」へ引き上げることができます。
 化学プラント大全
化学プラント大全