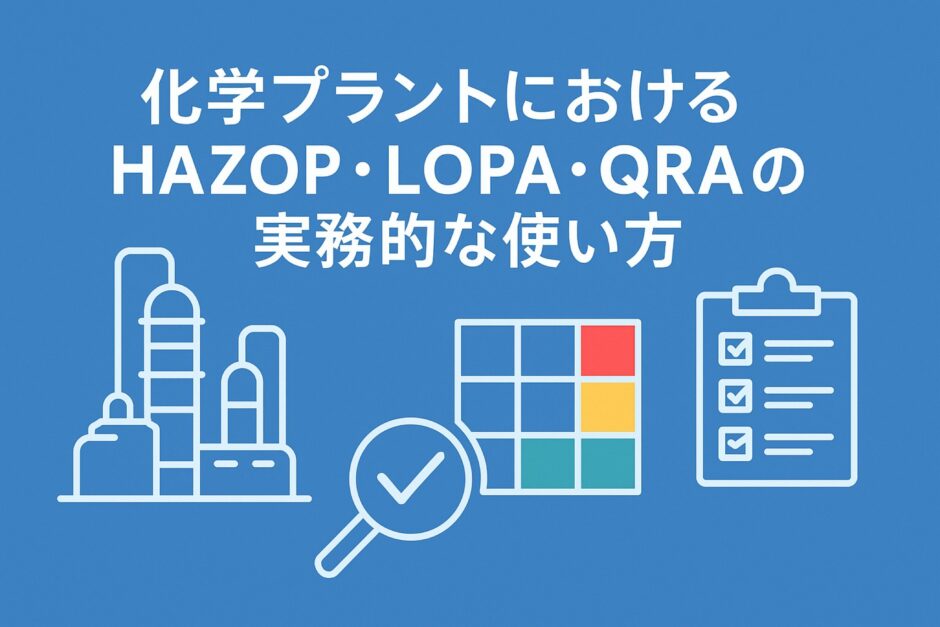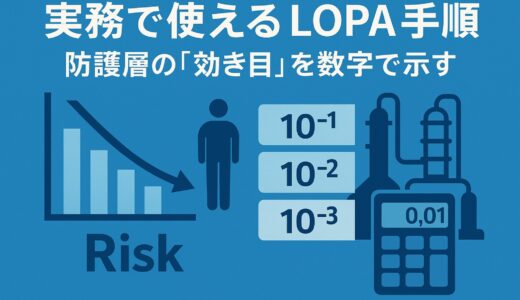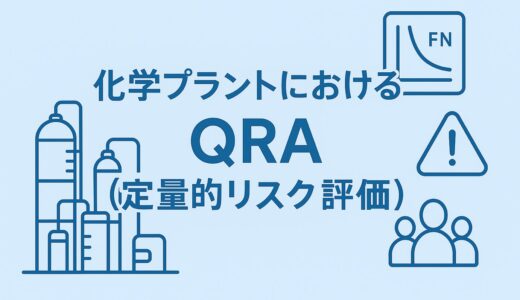化学プラントで事故が起きたとき、評価されるのは「事故を起こしたかどうか」だけではありません。
- どのようなリスクを認識していたのか
- それをどこまで低減していたのか
- 残ったリスクをどう社会と共有していたのか
という 「説明の質」 が、企業への信頼を大きく左右します。
本稿では、HAZOP・LOPA・QRA という代表的な安全工学の手法を軸に、化学プラントにおける リスクの“見える化”と説明責任 について整理します。
1. なぜ今、「リスクの見える化」が問われているのか
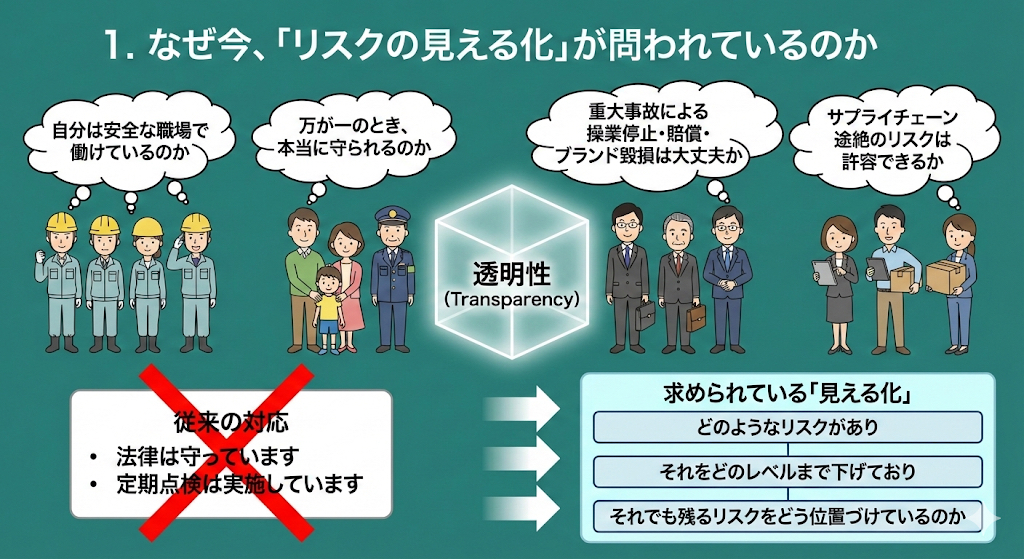
事故情報・内部告発・SNS による情報拡散などにより、企業はこれまで以上に「透明性」を求められています。特に化学プラントでは、次のようなステークホルダーがそれぞれ異なる不安を抱えています。
- 従業員:
「自分は安全な職場で働けているのか」 - 地域住民・自治体:
「万が一のとき、本当に守られるのか」 - 株主・金融機関:
「重大事故による操業停止・賠償・ブランド毀損は大丈夫か」 - 取引先・顧客:
「サプライチェーン途絶のリスクは許容できるか」
こうした問いに対し、「法律は守っています」「定期点検は実施しています」といった対策の羅列だけではもはや不十分です。
求められているのは、
- どのようなリスクがあり、
- それをどのレベルまで下げており、
- それでも残るリスクをどう位置づけているのか
を、誰にでも理解できる形で“見える化”し、説明できることです。
2. 企業が果たすべき「リスク説明責任」
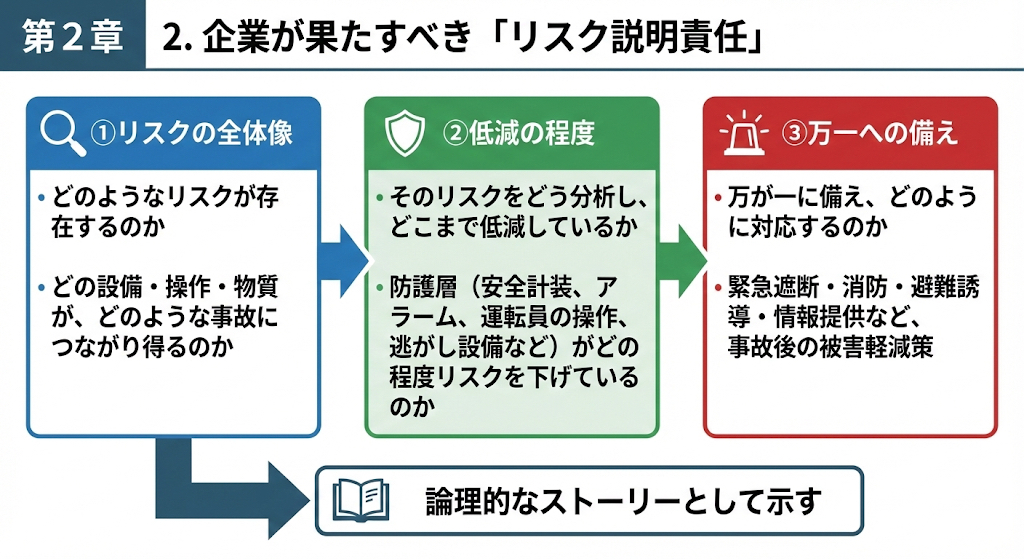
化学プラントの運営者は、社会に対して少なくとも次の3点を説明する責任があります。
- どのようなリスクが存在するのか
どの設備・どの操作・どの物質が、どのような事故につながり得るのか。 - そのリスクをどう分析し、どこまで低減しているか
防護層(安全計装、アラーム、運転員の操作、逃がし設備など)が
どの程度リスクを下げているのか。 - 万が一に備え、どのように対応するのか
緊急遮断・消防・避難誘導・情報提供など、事故後の被害軽減策。
この「①リスクの全体像 → ②低減の程度 → ③万一への備え」を論理的なストーリーとして示すことが、リスク説明責任の中核です。
 【詳細記事】安全計装システム(SIS)の基礎!DCSとの違いやSILの考え方を徹底解説
【詳細記事】安全計装システム(SIS)の基礎!DCSとの違いやSILの考え方を徹底解説
3. HAZOP・What-if による「ハザードの見える化」
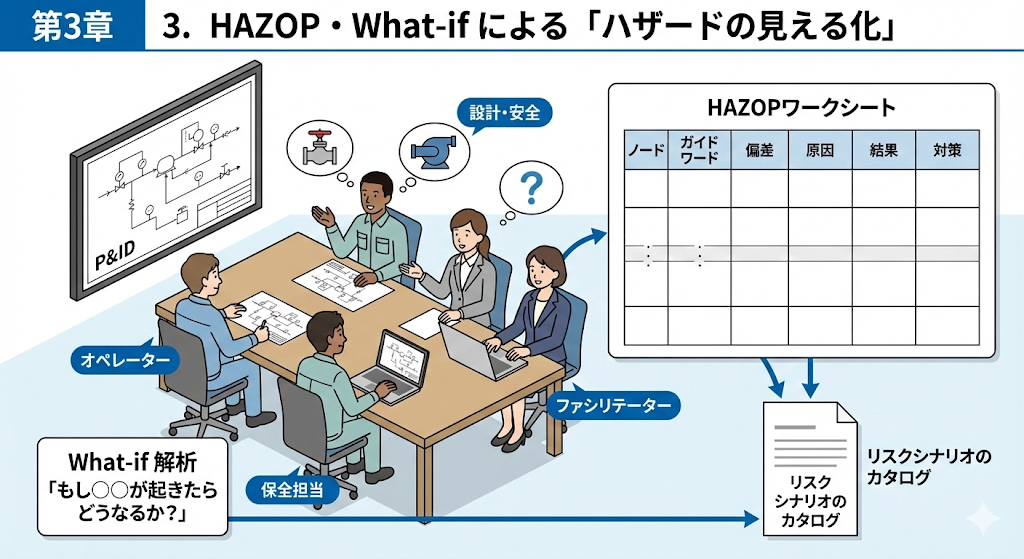
3-1. 役割:何が起こり得るかを洗い出す
HAZOP(Hazard and Operability Study)は、プロセスの設計条件と運転条件を基準に、「逸脱」を系統的に洗い出す手法です。
- どのような異常が起こり得るか
- それがどのような結果(過圧・過充填・漏洩・反応暴走など)につながるか
を、ノード・ガイドワード・偏差・原因・結果・対策といった枠組みで整理します。
What-if 解析も同様に、
- 「もし○○が起きたらどうなるか?」
という問いかけに対して、シナリオを洗い出していきます。
ここでのアウトプットは、
- 「リスクシナリオのカタログ」
- 後続の LOPA・QRA の「入力データ」
となります。
3-2. 現場を巻き込んだ“見える化”
HAZOP・What-if の品質を左右するのは、現場運転・保全の知見がどれだけ反映されているかです。
- オペレーター:
実際に起こりやすい異常・ヒヤリハット - 保全担当:
よく壊れる機器・隠れた劣化要因 - 設計・安全:
設計限界・安全弁設定・SISロジック など
これらを一つのテーブル上で議論し、フロー図(P&ID)と紐づけた形で“見える化”することで、「机上の安全」ではない、実感のあるリスク像が得られます。
4. LOPA による「防護層と残余リスクの見える化」
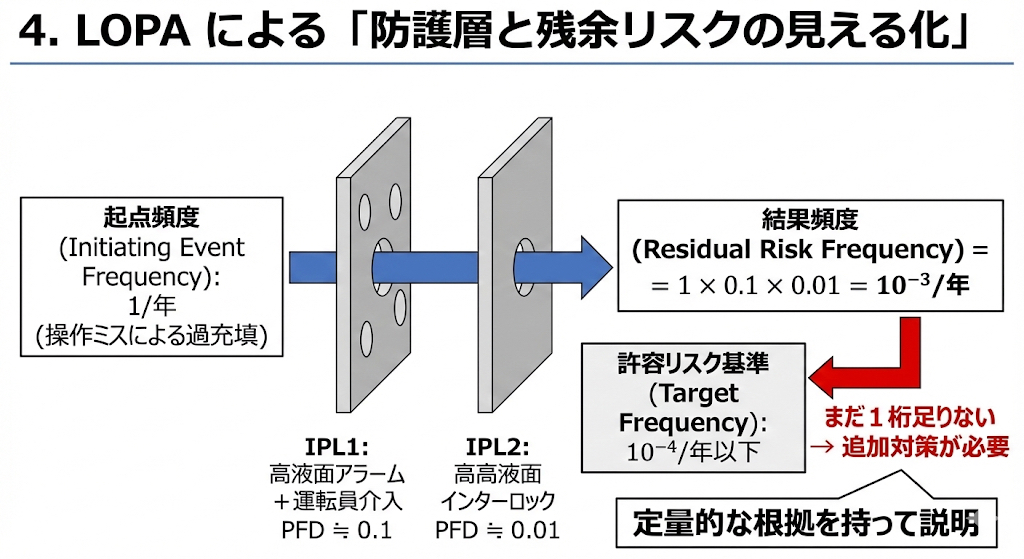
4-1. LOPA とは何か
LOPA(Layer of Protection Analysis)は、HAZOP で見つかった多数のシナリオの中から、
- 発生頻度と結果が重い「重要シナリオ」を選び、
- そのシナリオに対する**防護層(IPL: Independent Protection Layer)**が
- どの程度リスクを低減しているのか
を定量的に評価する手法です。
4-2. 「対策の数」から「対策の質」へ
従来ありがちな説明:
「異常時はアラームが鳴って、それでもダメならインターロックが効いて、最後は安全弁で守られます」
これでは、「たくさん対策がある」ことは伝わっても、
- それぞれどのくらい信用できるのか
- 合計としてどの程度リスクが下がっているのか
が分かりません。
イメージをつかみやすくするため、ここでは 仮の値 を用いて示します。
- 起点頻度:1/年(操作ミスによる過充填)
- IPL1:高液面アラーム+運転員介入(PFD ≒ 0.1 と仮定)
- IPL2:高高液面インターロック(PFD ≒ 0.01 と仮定)
と置くと、結果頻度 = 1 × 0.1 × 0.01 = 10⁻³/年となります。
さらに、例えばある企業が、「重大人身事故シナリオの許容頻度:10⁻⁴/年以下」という基準を定めているとします。
この場合、
- 現状:10⁻³/年
- ターゲット:10⁻⁴/年以下
となり、まだ 1桁足りない → 追加対策が必要という判断になります。
実務では、自社の信頼性データや国際的なガイドラインに基づき、
- 起点頻度の設定
- 各 IPL の PFD の設定
- 許容リスク基準(ターゲット頻度)
を整合的に決めていきます。
LOPA によって、
- 「なぜこのレベルの対策投資で打ち止めなのか」
- 「どのシナリオに追加投資が必要なのか」
を、定量的根拠を持って説明できるようになります。
5. QRA による「工場全体のリスクプロファイルの見える化」
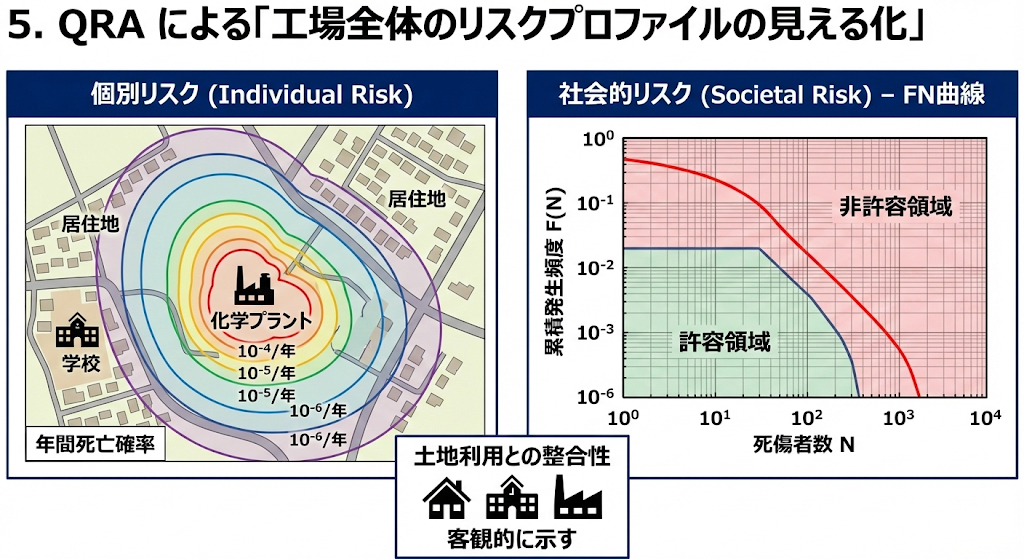
5-1. HAZOP・LOPA との違い
- HAZOP・What-if:
個々の設備・操作単位の「何が起こり得るか」の議論 - LOPA:
代表的シナリオに対する防護層・残余リスクの議論 - QRA(Quantitative Risk Assessment):
それらを踏まえた 「工場全体としてのリスク像」 の定量評価
5-2. QRA が見せてくれるもの
QRAでは主に次のような指標を使います。
- 個別リスク(Individual Risk):
工場境界や周辺居住地における「年間死亡確率」の等高線 - 社会的リスク(Societal Risk):
想定される死傷者数 N と、その 累積発生頻度 F(N) をプロットした FN 曲線 - 土地利用との整合性:
学校・住宅・商業施設などとリスク分布の関係
これにより、
- 「工場のどの方向・どの距離に、どの水準のリスクがあるのか」
- 「増設・能力増強をした場合でも、許容範囲に収まるのか」
を、行政・地域住民・投資家に対して客観的に示すことが可能になります。
6. ステークホルダー別にどう“見せる”か

同じリスク情報でも、相手によって表現を変える必要があります。
6-1. 経営層・取締役会向け
- Top10 リスクシナリオの一覧表
- 各シナリオの残余リスクレベル(リスクマトリクス上の位置)
- 投資・対策の優先度と費用対効果
- 重大リスクに関する KPI(SISテスト遅延件数、MOC遅れ 等)
→ 「どこに経営資源を投入すべきか」が一目で分かる形に整理します。
6-2. 現場・従業員向け
- 各ラインごとの 一枚ものリスクマップ
- 主な危険源(高圧・高温・毒性物質 等)
- 重要な安全装置と守るべき運転範囲
- 異常時の初動(止める/閉める/離れる など)
- 過去の事故例との紐づけ
「このシナリオを放置すると、○○事故と同じパターンになる」
→ 「自分の作業」と「会社が見ているリスク像」をつなぐことが重要です。
6-3. 地域住民・自治体向け
- 技術用語を極力使わず、図・イラスト多めで説明
- 想定している最悪シナリオ、その発生を下げる対策、万一のときの行動をセットで提示
- 防災訓練・情報提供の仕組みも併せて示す
→ 「何も隠さない」「一緒に備える」という姿勢が信頼を生みます。
7. 「見える化」の落とし穴と注意点
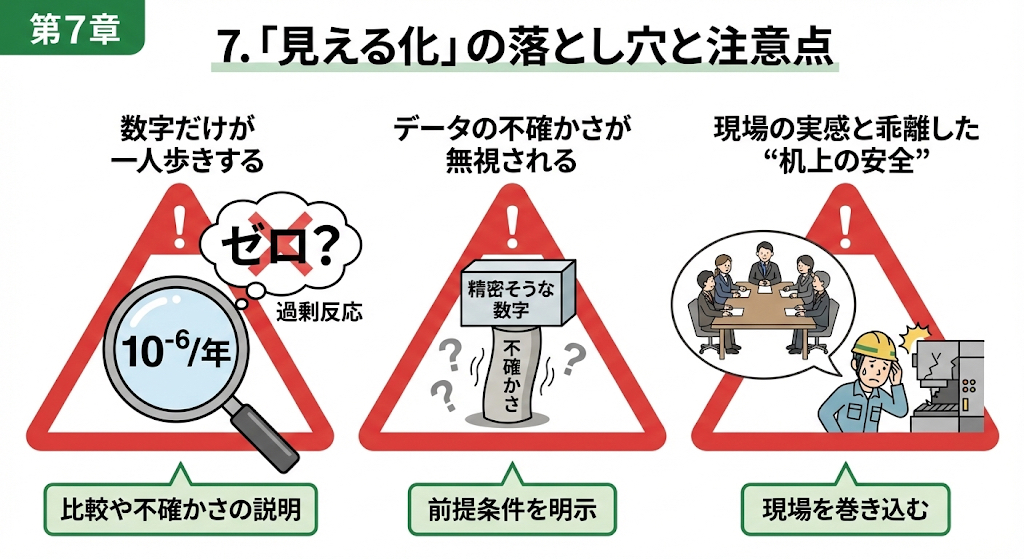
リスクを数字で示せるようになる一方で、次のような落とし穴もあります。
- 数字だけが一人歩きする
- 10⁻⁶/年を「ゼロ」と誤解する
- 逆に、わずかなリスクに過剰反応してしまう
→ 他の一般的リスク(交通事故など)との比較や、不確かさの説明が必須です。
- データの不確かさが無視される
- データベースや故障率に大きな幅があるにも関わらず、
「精密そうに見える数字」が一人歩きする。
→ 前提条件や保守的な仮定を明示することが重要です。
- データベースや故障率に大きな幅があるにも関わらず、
- 現場の実感と乖離した“机上の安全”になる
- HAZOP・LOPA を会議室だけで実施し、現場の声が入らない。
→ オペレーター・保全・安全の三者を巻き込み、定期的に見直すことが不可欠です。
- HAZOP・LOPA を会議室だけで実施し、現場の声が入らない。
8. 化学プラントで「リスク見える化」を進める実務ステップ
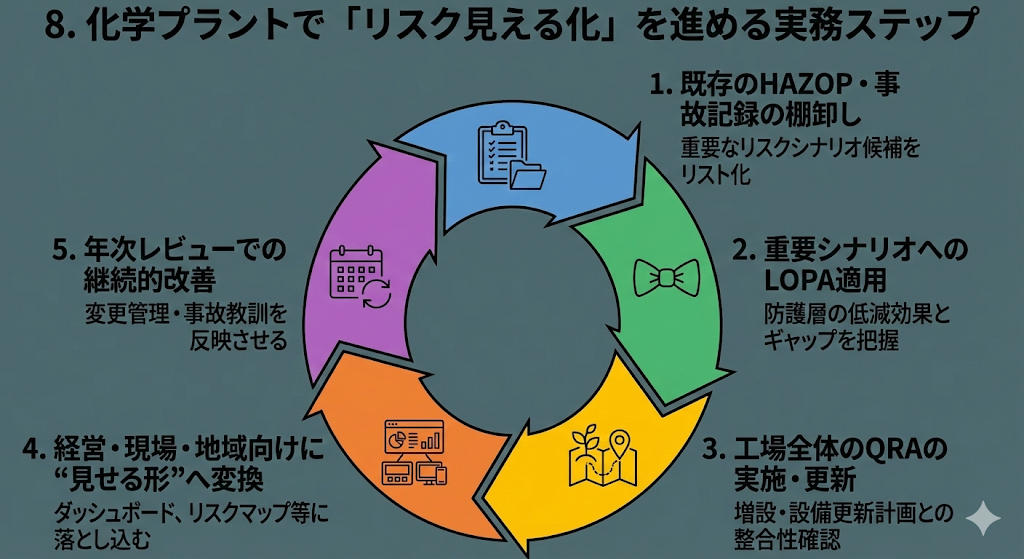
最後に、実務としての進め方を簡潔に整理します。
- 既存の HAZOP・事故記録の棚卸し
- 重要なリスクシナリオ候補をリスト化する。
- 重要シナリオへの LOPA 適用
- 現有防護層のリスク低減効果とギャップを把握する。
- 工場全体の QRA(もしくは簡易評価)の実施・更新
- 増設・設備更新の計画との整合性を確認する。
- 経営・現場・地域向けに“見せる形”へ変換
- ダッシュボード、リスクマトリクス、ボウタイ図、リスクマップなどに落とし込む。
- 年次レビューでの継続的改善
- 変更管理・ヒヤリハット・事故教訓をリスクプロファイルに反映させる。
おわりに:残るリスクをどう社会と共有するか
「リスクの見える化」とは、事故が絶対に起こらないと宣言することではありません。
- どのようなリスクがあり、
- それをどこまで低減しており、
- それでも残るリスクをどう受け止め、どう備えているのか
を、正直かつ体系的に示し、ステークホルダーと共有する 対話のプロセス です。
HAZOP・LOPA・QRA は、そのための 道具箱 に過ぎません。
 化学プラント大全
化学プラント大全