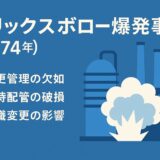化学プラントでの事故は、一見すると“突然発生する”ように見えます。しかしその裏側では、設備劣化・検知遅れ・非定常運転など、さまざまな要因が静かに蓄積しています。
本記事では、直近3か月(2025年8月〜10月)に発生した日本国内の重大3事故を取り上げ、技術者にとっての学びを整理します。
取り上げる事故は以下の通りです。
- 関東電化工業 渋川工場(爆発・火災/1名死亡)
- 日本カーボン 富山工場(黒鉛化炉火災/焼損4,400㎡)
- 三井化学 大牟田工場(塩素系ガス漏えい/住民234名受診)
1. 関東電化工業 渋川工場 爆発・火災
(2025年8月7日/群馬県渋川市)
➡ 可燃性ガスによる爆発で1名死亡・1名負傷
可燃性ガスを扱う設備建屋で爆発が発生し、火災へ拡大しました。若手従業員が死亡する、大変重い事故です。
▼ 情報源リンク
- 公式公告(関東電化工業)
https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20250916/20250916558493.pdf - テレ朝ニュース
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000444870.html - Bloomberg(半導体関連への影響)
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-08-13/T0WZW0GP9VD300
▼ 学び
- 可燃性ガスは「閉空間 × 漏えい × 点火源」で一気に爆発モードへ。
- 定常運転より、立上げ・停止・メンテ・洗浄時の方が危険性が高い。
- 換気・爆発放散・可燃性ガス検知の信頼性が重要。
2. 日本カーボン 富山工場 黒鉛化炉火災
(2025年8月29日/富山県富山市)
➡ 焼損4,400㎡、57時間に及ぶ大規模火災
黒鉛化炉内でガス発生が急速に進み、炉の内圧が上昇。
高温炭素粒子が噴出し建屋火災に発展したことが会社から公表されています。
▼ 情報源リンク
- 公式発表(日本カーボン)
https://www.carbon.co.jp/topics/topic_20251014_jp.pdf - TBS NEWS DIG
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2141607
▼ 学び
- 高温 × ガス発生 × 粉体(炭素) の複合ハザード。
- 爆発ではなく「異常反応 → 圧力上昇 → 飛散 → 火災」の連鎖型事故。
- ベント設計・耐火構造・異常反応監視の仕組みが重要。
3. 三井化学 大牟田工場 塩素系ガス/液体漏えい
(2025年7月27日・9月8日/福岡県大牟田市)
➡ 住民234名が医療機関受診する社会的影響事故
▼ 7月27日:塩素系ガスが敷地外へ拡散
TDI工程で塩素系ガスが漏えいし、周辺住民・通行者など234名が医療機関を受診しました。
▼ その後の進展
- 9月8日:別ラインで塩素系液体が漏えい(人的被害なし)
- 11月4日:労基署がボイラー等に関する「特例認定」を取り消し
事故が1回で終わらず、複数インシデント → 行政処分へ進む典型例です。
▼ 情報源リンク
- 三井化学:お詫び文書(PDF)
https://jp.mitsuichemicals.com/content/dam/mitsuichemicals/sites/mci/documents/jp/corporate/notice/pdf/250728.pdf - 三井化学:対応状況(第8報)
https://jp.mitsuichemicals.com/jp/release/2025/2025_0903/index.htm - FNN(特例認定取消)
https://www.fnn.jp/articles/-/955407 - NEWS DIG(塩素系液体漏えい)
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2158481
▼ 学び
- 塩素は少量の漏えいでも敷地外影響へ直結しやすい。
- 配管腐食・シール劣化など「設備劣化」が本質的リスク。
- 一度事故が起きると、同一拠点で潜在不良が顕在化しやすい。
- 事故後は HAZOP・LOPAの前提条件を必ず更新 する必要がある。
4. 3事故の共通項:プロセス安全に必須の観点
① 設備劣化は最大の潜在ハザード
特に塩素など腐食性物質では、局部腐食が突然進展することがある。
② 非定常運転(立上げ・停止・洗浄)が最も危険
多くの重大事故は定常運転中ではなく、非定常状態で発生している。
③ 敷地外影響があるかどうかで、求められるレベルが変わる
住民対応・消防連携・拡散モデリングなど追加対策が必要。
5. 明日から現場で使えるチェック項目
- 配管腐食(塩素・酸・高温ライン)のUT・GW・内視鏡点検
- ガス検知器の配置と閾値の妥当性
- 自動遮断弁の定期動作テスト
- 立上げ・停止のリスク分析(KYT+HAZOP補完)
- 異常反応を検知する指標(圧力上昇速度・温度プロファイル)
- 敷地外影響シナリオの再評価(モデリング含む)
まとめ:事故ゼロの週こそ「安全」を深めるチャンス
事故は“その工場だけの問題”ではなく、同じ物質・同じ工程・同じ設備を持つ全ての工場の教訓 になります。
外部事故を自社設備に当てはめて考える習慣こそ、プラントの安全文化を確実に成熟させる力になります。
 化学プラント大全
化学プラント大全